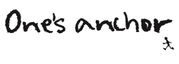木綿(もめん)
日本に、木綿がはいってくるまえの衣料は麻だったといいます。
宮崎安貞は農業全書(元禄10年1697年刊)のなかで麻のことを次のように書いています。
「むかし、木綿が普及するまでは庶民はいうに及ばず、貧しいサムライなど絹を着ることができないものは、ただ、麻布をもって衣服の代わりとした。
この麻布の服は、寒気をふせぐのがむずかしく、みな困苦していた。
たとえ、上に仁政を敷くものがいたとしても、ようやく五十歳をこえてから絹をきてもよいという政令のみで、それより下の者は麻しか着ることができなかった」
いわゆる、戦国時代に、火縄、旗、船の帆などに木綿をつかったため、外国から大量に綿製品を輸入するようになりましたが、多くの人の衣類は麻のままでした。
それが江戸時代になり木綿栽培の普及によって、大きく変わっていきました。
安貞はつづけて次のように述べています。
「幸い、綿の栽培がひろがり、それが山奥の木こりまで綿の衣類をまとうようなことになるとは、誠に天恩のなすところにして、これすなわち天下の霊材というべし」
綿は「天下の霊材」とよぶほど革新的な素材だったのです。
これは産業革命発祥のイギリスでも事情は同じです。
木綿は栽培、加工がしやすいうえに、肌にあたったときの素材の心地よさもあって綿が浸透するエネルギー、スピードはともに絶大でした。
18世紀前半、イギリス人のジョン・ケイはフライングシャトルという機織りの横糸をハンマーの反動で行き来させる道具を発明しました。従来の手動にくらべ織る速度が飛躍的に増し、このフライングシャトルが普及していくにしたがい糸不足をまねきました。
しかし、その糸不足をおぎなう発明が次々となされ、技術は矢継ぎ早に更新されました。
産業革命に火がついたのです。
動力は人力から家畜、ついで水力、そして蒸気機関へと発展していきました。
綿の「霊材」としての需要はそれほどの力を持っていました。
同じころの日本も綿がいきわたりはじめた時期でした。
江戸時代、大坂、京は全国でも有数の綿、もめん布の産地でした。
綿栽培の立地条件の悪い、東北、北陸、九州は、近畿から大量の綿を買い入れて、糸をつむぎ、織物をつくりました。
綿製品がいきわたりはじめると、こんどは、三井などの問屋商人が、あたらしい商売の方法をかんがえだしました。
それまで問屋商人は商品をはこぶことで、お金をかせいでいました。それを自分で商品を買いとり、運搬し、販売して、かせぐ形をつくりだしました。コストは高くつきますが、莫大な利益をよびました。
18世紀前半で、ちょうど、綿製品が急速にのびていった時期にあたり、このような新しいタイプの商人に多くの資金が集まるようになりました。
綿製品をたくさんつくる農村では、農作業をせずに糸をつむぐ人、織る人があらわれました。分業がはじまったのです
こういった人たちは、資金が豊富な問屋商人に、お金をかりて、機具をかいました。
借金をして機織機などの器具を購入しましたが、綿の普及する力はすさまじく返済してなおかつ利を生みました。
やがて、幕末になると、この綿織職人の集落は問屋商人の力を借りなくてもいいほど、綿工業は発展していたのです。
明治になって外国とのとりひきがはじまると、大量の綿製品が、国内に入ってきました。
日本は一時、隣国の清、インドといった大国をしのぐほど、急激に綿製品を輸入したのです。日本における綿製品の40%は輸入ものがしめるまでになりました。
そのあと、国産の綿製品がもりかえし、19世紀末には輸出するようにまでなりました。一時期は生糸と並んで、日本の重要な輸出商品となります。
この輸入から輸出に反転した理由は、日本にはさきに書いた通り全国に綿工業の基礎ができあがっていたことがあげられます。
国内では織って反物をつくることがさかんだったため、不足しがちな国産の糸を外国製の糸にかえました。これが、輸入増大につながった原因でした。
糸をつむぐひとは失業しましたが、農村が吸収しやがて工場労働者として再び都市へ排出されます。大規模工場ができてからは、国産の糸が増大していきました。
それから、輸入品が日本の農村の嗜好に合わなかったということあります。
農村では輸入品よりももっと厚手で丈夫なものを求めていましたが、そのような綿製品を作る技術は日本にしかありませんでした。需要と供給のエリアは日本の中にあったのです。
木綿には、かように経済を発展させる「天下の霊材」という力もあるようです。