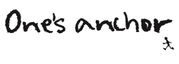戦後福祉の出発点
戦後の福祉政策は、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が大きな影響をおよぼしたと云われている。
GHQはそれまでの、封建階級でいう庄屋や戦前の区長といった階層が国家と民衆の中間に位置し、国の定めた制度を円滑に普及させ、同時に民衆の声をすくい上げていった構造を廃止させ、かわりに国が直接、地方に窓口を作る方法に変更した。
これは、「無差別平等」と「公私分離」というGHQの方針からだされた方策である。その本質的な狙いは、軍国主義の放逐であり、民主国家の樹立である。
敗戦国が、戦勝国から国のありようを決められるのは、やむを得ないし、いまとなればその方向性は間違っていなかったといえるが、戦前の構造が全て非効率的だとは思えないところもある。
戦後の混乱時に米国の宗教団体、労働団体が主導したララ物資といわれる、日本への救援物資は「公平」「迅速」「効果的」という三大モットーのもとに実施されたが、物資が無駄なく全国にいきわたったのは、先の中間層の役割が大きいのではないかと思う。単に物資を配布するのではなく、中間層が各家庭の実情にあわせてアレンジして配ったからである。村落共同体の実情をよく知る階層が存在していたのだ。
明治維新によって、日本という国民国家が誕生したが、敗戦はその国民国家の無差別性をより徹底しておこなった。それが、封建遺制といわれた中間層の解体である。戦後の農地改革にその意図がもっともよくあらわれているが、福祉の側面からもそれは見て取れる。
敗戦の翌年、生活保護法が制定された。戦前の救護法、母子福祉法、軍人扶助法ほかを一括した総合福祉法といえるもので、無差別平等を基本とした法律だった。しかし、GHQは、この法律に難色を示す。
ひとつは方面委員から名称の変わった民生委員が保護の要否を決定すること、保護の客観的な基準が曖昧だったこと、また欠格事項(勤労能力があるにも関わらず勤労の意思のないものなど)があることなどを挙げ、国の責任で保護の要否の基準をより明確にし、生活保護は国民の権利(憲法で定められた生存権)であることを日本国に求めた。
方面委員というのは、学区ごとに設置され、その地域の生活困窮者の実態を調べ、助言する無償有志の委員のことで、いまの民生委員と役割はあまり変わらないものの、知事の名誉職という役職柄、地元の名士、つまり共同体の中間層がその役割を担っていた。GHQは実情としては地域に密着しているこの方面委員(民生委員)という曖昧な存在を嫌い、その役割を国が直接になうことを志向する。
GHQと厚生省の協議の結果、1950年に今の生活保護法が成立する。
いまも、各自治体に福祉事務所が置かれているが、この福祉事務所こそ単一の全国的政府機関であり、方面委員という中間層をはぶいた戦後福祉の出発点であった。生活保護の要否はこの福祉事務所に配置された社会福祉主事が有給専任であたり、生存権の具体的な行使が保護請求権であることも明記された。
このように、それまで機能していた中間層を取り除くことで、公の責任の所在を明確にし、保護要件の基準をはっきりさせること、不服申立てを採用することで恣意的な運用を防ぎ平等性の担保とした。
これが、GHQの目指した方向であり、民主、平等の具体的なかたちだった。