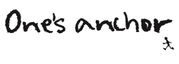教育や看護、福祉といわれる分野は、いわゆる専門性が重視されます。そのための学校があり、職業的な経験値が必要とされています。
この3つの分野は、いずれも人とのかかわりが職務の中心にあるという共通点があり、近代以前には家庭が主ににない、村落がささえたという側面もにています。
もともと近親者や親類、近所の人たちが子どもたちを育て、たがいに面倒をみるという自然なかたちが、産業の発展に伴い分化していき、いわゆる専門職といわれるようになりました。
産業の発展に伴い分化する、ということは、同じ特徴をもつ人を一か所にあつめるということであり、先生と生徒、看護者と病者、介護者と障害者という社会的な立場をわけることになります。
近代以降は、こうした分化したかたちがふつうになりました。先生、看護師、介助者という職業は選ぶもので、あえて引き受けるものではなくなったのです。
ただ、実生活では、親はこどもを教育し、身内のだれかが病気になれば看護し、障害があれば介助しますから、だれかが誰かを頼り、頼られるという関係は、現代になって弱まっていると指摘されているものの、いぜんとして人間関係の根っこにあります。
看護や教育、福祉の仕事で、目の前のひととじゅうぶんに関わりを持とうとすると、かならず生活をふくめた全人格的な関与を目指してしまうのは、このような人間関係の根っこに理由があるのかもしれません。
糸賀一雄は、「生活と教育を相即させ」る施設として、戦後の混乱期にいち早く近江学園を設立しました。
その人の生活も含め、自分自身もその全人格をかけてかかわりを持つことで、理想の教育を実現させようとしたのです。医療部門を設置し、研究部門を主要な柱とするなどその取り組みは徹底していました。
ここに、社会的な関係のなかで人が人と関わろうとするときのはっきりとした方向がみてとれます。つまり、部分ではなく全体を目指すのです。
運営面でも同様で、三条件といって「四六時中勤務」、「耐乏生活」、「不断の研究」、つまり「子どもたちがいるのだから休みはなし」「互いの稼ぎで互いが食べていくのだから、怠けているものは馘首(クビ)」「新任は研究部門で鍛えられ、優れたものが採用される」といったきびしい条件を課しました。
この三条件をふくめ、職員の給与を全額、園の運営費と生活費に当てるなど、全身で奉職することをもとめ、園という組織がその人の老後まで面倒を見るという、あきらかに擬似共同体を目指していましたといえます。
ただ、近代以前は、地縁血縁で濃厚に関係が作られていたのに対し、糸賀の構想はあくまでも人工的でした。
そこに、ひずみがあったのでしょう。
理念に共感して就職を希望した者でもやむをえず離職し、あるいは馘首を申し渡され、わずか5年半で64名の職員がはなれていきました。
理想を現実のものとしたはずでしたが、そこには苦悩も多くありました。
糸賀は戦前、戦中と滋賀県庁や学生義勇軍同志会などのはたらきで高く評価され、志を一つにする同志にもめぐりあえました。初期の近江学園をささえたのは、これらの同志です。
しかし、あらたな同志を得ることはなかなか難しいことでした。
ここに、同一体験を経たものとそうでないものの断絶を感じます。
どれだけ苦しくても、それを乗り越えた同世代の人たちとは、多少の意見のくいちがいあっても共感をえることができます。しかし、世代が下るとどうしても異物がはさまった感覚を持ってしまいます。
これは下の世代も同様の感覚をもつものです。「あたりまえ」の感覚がズレてしまうのです。
革新的な事業は、宿命的にこうしたズレを内包してしまうのでしょう。