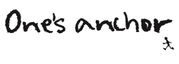わたしは、むかしの障害者はどんなふうに生きていたのだろうと思うことがあります。
「むかし」といっても3,40年前は実体験として覚えています。それよりももっと前、たとえば戦前とか江戸時代とかです。
それで調べてみたりするのですが、断片的なことしかわかりません。その一部を記します。
1697年に刊行された「農業全書」という日本最古の農書のなかで、著者の宮崎安貞は「手足の不具なる者」や虚弱な人にアヒルを飼うことをすすめています。アヒルの卵を売って生計のたしにすればよいといっているのです。
その書き方はだいたいこれぐらいになるだろうという計算があり、文面に慮っているところがあって、手足の不自由な人達に対するやさしい視線があります。
秋田藩では感恩講といった互助的な仕組みで孤児や貧民救済をおこなっていました。
近代以前において社会における最大の危機は飢饉でした。平安時代後期の飢饉では鳥羽上皇が京都、鴨川の河原で自分の所有する荘園から米を持ってきて緊急にふるまったとの記述があります。
ようするに江戸時代から前は、集落がひとつの生命体のように、弱いところを補い、もつものを分けあって存続してきた。そのなかに障害のある人、高齢者、乳児は隔てなくふくまれていた、といえるのではないでしょうか。
では、近代に入った明治から敗戦まではどうだったのか。
ここがまた、よくわかりません。
大正時代の俳人、富田木歩は下半身が不自由でした。そのため不就学でずっと家にいました。大きくなってから駄菓子屋の店番をしたり、帽子の裏地を縫い付ける内職をしたりしていましたが、基本的に家族が彼の不自由な面をおぎなっていたようです。
明治以降、近代化のなかで、都市がうまれ農村はその食料と労働力の供給地でした。
江戸時代にすでにそのような構図はできあがっていたのですが、工業化が進むなかで、「労働者」というあたらしい種類の階層ができあがり、以前のように村落共同体が弱いところをフォローするということができなくなりました。
おそらく近代において高齢、病気、障害をもつ人のケアは家族、親族単位でおもに女性が担っていたのでしょう。
近代は現在にいたるまで男性を社会の労働力として、女性を家事労働の担い手として分化してきたからです。
そして、家族のいない人たちは、篤志家や宗教団体の主宰する施設で暮らしていたということではないか思います。
ただ、そのなかで視覚障害と聴覚障害のある人に対しては明治の早くに京都で専門の学校が開校し、伝統的な職業に就労していきました。また、戦争で障害を負った人は国がリハビリテーションをおこない社会復帰の道すじをつけていました。
それ以外の障害者は、家から出ることもなく、「障害者をとりまく問題」という概念はでてきようがなかったのではないでしょうか。
戦後、「障害者をとりまく問題」があらわれたのは、分散していた一部の障害児が集められたからでした。
敗戦後の混乱期に多くの戦災孤児が生まれ、そのなかにすくなからず知的障害児がふくまれていました。
やがて、戦災孤児と障害児はちがった違った処遇が必要だということになり、いわゆる「障害児をとりまく問題」がうかびあがってきます。
身体に障害を持っていたり、重複した障害を持った子どもたちは、また、違ったところに集まっていました。