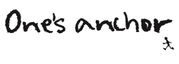このところ戦後の福祉の話題が続いていたので、閑話休題でお酒のはなしを。
日本酒は保存がむずかしい飲み物でした。
腐りやすいのです。
そのため、江戸時代以前から「火入れ」という手法をとりいれるようになりました。
「火入れ」というのは、生酒を60度から65度ほどまで煮る工程のことをさします。
この「火入れ」は当初、夏に作られた酒にだけ用いられ、その後、冬に作られた酒にも取り入れられるようになりました。
近世では江戸が最大の酒の消費地ですが、酒造りは関西が主でした。「火入れ」という技術を考えたのも関西の酒蔵です。しかし、火入れによって保存をよくしたものの、伊丹や池田から江戸まで送るあいだになお腐ってしまう酒は多かったようです。
そのうち焼酎を酒にまぜて江戸に送るようになりました。焼酎がアルコール度数をあげて腐敗防止に役立つのだそうです。
この焼酎を混入させた酒は江戸で「辛口」と評され広まっていきました。
江戸時代の後期にはこの「辛口」がブームとなって日本酒の消費を押し上げました。その消費をささえたのは伊丹、池田の酒造業者ではなく、灘の新しい酒でした。
精米の割合をそれまでの倍にしてよりアルコール度数の高いお酒を作りました。
それでも、なお、お酒の腐敗という課題は残りました。
時代が明治になりヨーロッパの新技術がおおく輸入されるようになりました。
そのなかで、当時ドイツで開発されてまもない「サルチル酸」という薬品が酒の防腐に有効であると東京大学に赴任したドイツ人教師が発表しました。
効果はてきめんだったようで、いっきに「サルチル酸」が用いられるようになりました。
「サルチル酸」というのは解熱鎮痛に効果があるほか、肉や牛乳などの防腐効果も伝えられていました。
これでようやくお酒の腐敗の問題は解決したかに思われましたが、明治36年に内務省が「飲食物防腐剤取締規則」を発令し、他の薬品とともに「サルチル酸」の使用を禁止します。
人体に悪影響をおよぼすというのです。
完全禁止までには7年の猶予がありましたが、なんの手がかりもないまま完全な防腐技術というものがはたしてあるのだろうかと、当時の清酒業者は暗澹たる気持ちになったとのことです。
そのなかで、伏見で長らく酒を作ってきた大倉常吉商店(現在の月桂冠株式会社)は独自に研究所を設立し、明治44年、防腐剤のない酒の生産に成功しました。
その手法は、腐敗菌の抑制に焦点をあてたもので、現在の食品管理につながる考え方といえます。
つまり、工場内の洗浄箇所、清掃方法、加熱殺菌の温度などを詳しく調べた上で徹底管理し、杉のタルが主流だった当時、ビンに切り替えるということです。
ビンの使用はこれに先たつ20年ほど前、国産のビール瓶が製造され、その十年後に一升瓶の清酒が販売されましたが、まだ普及するにはいたらなかったのです。
幕末の鳥羽伏見の戦いで一度は灰燼に帰した伏見の酒造でしたが、明治44年から売り上げを伸ばし続け、大正8年には倍の数量を売り上げるまでになりました。
その一因は全国に先駆けて開発した防腐剤不使用の清酒の大量製造にあるといえます。