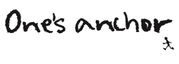ベルギーで起こった、サリドマイドの赤ちゃん殺しをきっかけとした婦人公論の座談会「誌上裁判 奇形児は殺されるべきか」で、作家の水上勉は、障害のある人の中でも「社会にプラスすることができない場合は人の範疇に入らないのではないか」と述べています。
そして、戦後いち早く重症心身障害児の療育をはじめた小林提樹につぎのように問います。
水上「その子が生きても社会にプラスすることは一ミクロンもないと思われるお子さんがいらっしゃいますか」
小林「おります。しかし、明らかに育ててよかったと思うことがずいぶんあります」
水上「社会にプラスしないということはかわりないでしょう」
小林「社会にプラスするかしないかは考えません」
小林は、戦後まもなくから「独立自立」の対象にならないとされた重度の障害をもつ乳幼児を病院で引き受け、その後いくたの困難を経ながら、島田療育園の設立に尽力しました。
その濃厚な経験がはっきりとした意思となりこの発言につながっています。
この座談会で小林は障害児殺しに対する否定の意見を控えめにですが明確に述べています(胎児に対しては別ですが)。
一方、水上勉は障害をもつ娘の父であり、のちに「拝啓池田総理大臣殿」を記し、その後の福祉の方向に一定の影響をあたえました。その彼は、冒頭に書いたように障害のある子の一部は「人間」の範疇に入らない、また、生命審議会を作ってもらってそこで子どもの生死を決定してほしいともいっています。
水上は、自らの娘に障害があるとわかったとき、なんとかして生かそうと奔走しました。そのような経験のある水上がなぜ障害のある子どもの抹殺に加担するような発言をするのでしょうか。
座談会を読みすすめていくと次のような箇所にあたります。
水上「その奇形の子を太陽に向ける施設があればいいが、そんなものはない。そうした今の日本では、どうしても生かしておいたら辛いんだな。親も辛い、子も辛かろう」
つまり、障害をもつ本人もその親族も生きていくのが悲惨だからというのが発言の根本にあるようです。
座談会では当時(昭和37年)の様子を、わずかながら施設、教育設備はあるものの重度あるいは重複障害のある人は受け入れてもらえない、そういった人は親がかかりになるが、親が亡くなったあとは短命に終わるといいます。叫び声も出せないのでいつの間にか社会から消えていくのだというのです。
ここから、一足飛びに社会にプラスにならないのなら人間範疇にはいらないのではないかとの発言につながります。
重度の障害を抱えた人たちの現実はあまりに悲惨だから、その命の価値に軽重をつけ、その結果、人間の範疇に入らないと考えられる人は嬰児の段階で抹殺したほうがいいのではないかという意見を披露するのです。
ただでさえ、「いつの間にか社会から消えていく」人たちにたいして、人間の範疇にはいらないといい、そして死してもやむなしという思考は寒気を感じます。
天空を仰ぎ見て安堵する瞬間や寝顔を見て微笑むひとときといった、苦しさを生きていくうえでだれもがもつべき日常生活の機微がここにはないからです。
座談会のなかで水上の発言は障害児を抹殺すべきという論調で突出しています。
その意味で水上の発言を当時の多数意見とは思えませんが、優生保護法における優生思想や障害児殺しなどを考えると当時は「否定しがたい」発言だったのかもしれません。
次回は、この座談会における小林提樹の発言に注目をしていきます。