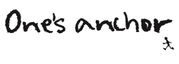かつおは、腐りやすいため、むかしから、おおくは煮たり、煮たものを干して、食べていました。
そのため、はやくから、その煮汁は、こくがあり、風味のよいことが知られていました。
江戸時代の初期の料理本には「かつお節1升に梅干を15~20個ほどいれ、古酒2升に水とたまり醤油を少し入れて、1升になるほど煎じてこし、さませばよい」と書かれてあります。
これは、「煎り酒」という、むかしの調味料です。
作り方は、これだけではなく、さまざまな調合の煎り酒がつくられていました。
もっとむかしは、煎汁(いろり)という、かつおを煮詰めて濃縮した汁が、朝廷への献納品としてあったそうです。
かつおは腐りやすい魚といわれていますが、なまでも食べられていました。
刺身は酢醤油やからしみそにつけてたべていたそうです。
また、丼物をつくるときは、かつおをおおきめに切り、山芋をすりおろして、大根おろしの絞り汁と酢醤油であえたものをかけたそうです。
おいしそうですね。
なまのかつおは、くさみがあるため、酒や酢、さきほどの煎り酒のほかに、わさび、からし、みょうがなども、におい消しに使われていました。
かつおは、そうやって、さまざまな食材とあわせて食べることができるので、人気があり、特に初鰹は、買い手があふれ、値段が高騰し、幕府が禁令をだしたほどです。
かつおのたたきは、現在ではわらであぶったかつおを氷水でしめる半なまの食材ですが、むかしは、ちがう料理のことを「たたき」と呼んでいました。
かつおの身をたたいて、多めに塩を入れ、紙でふたをして、日なたに出しておいて、日に5回ほどかき混ぜ、10日もすればできあがるものを「たたき」とよんでいたのです。たしかに、こちらのほうが「たたき」という名前にあっていますね。
いまの「たたき」に近いものは、「当座なまりぶし」とよばれていました。
しかし、いまでは、「なまりぶし」はかつお節のことをさします。時代がくだるにつれて呼び名もかわってきたようです。
そのかつお節は、煮て干したあと、燻製にした「荒節」と、さらにカビをつけて、水分をとばした「枯節」に分けられます。
もともとは、「荒節」だけでしたが、土佐でコウジカビをつけた「枯節」が開発されました。
そのため、土佐節とよばれた、このかつお節は、だれもまねのできない、独自の物産としての地位を占めました。
しかし、かびつけの工程は、門外不出の秘伝だったものの、当の土佐の人間が、伊豆や薩摩にその秘伝をつたえてしまい、秘伝ではなくなってしまいました。
その後も、カビつけには工夫が凝らされ、4度のカビつけをおこなう「本枯節」でかつお節は完成されました。
株式会社にんべんは、300年前に創業した当初から、かつお節をあつかっていますが、その社内資料に「本枯節」は伊豆田子で完成したとの記述があるそうです。