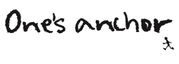わたしが「青い芝の会」の存在を知ったのは、本多勝一の「貧困なる精神」という本からです。
当時、わたしは小さな大学の社会福祉学科に在籍していて、在学生のなん割かは、いわゆる福祉の現場とつながっていました。ボランティアやアルバイト、あるいはサークル、クラブといったかたちで。
とうぜん、そこには「障害児・者」とのかかわりもふくまれていました。
わたしは、大学のかたすみの手話サークルに属している一方で障害者の裁判を支援したり、障害者の全国組織に参加したりと、いわゆる「福祉の現場」にも顔をだしていました。
学生というのは、比較的時間に余裕があって、ともだちとよく話をします。
まだ、社会経験が貧弱なので、はなしのなかみは、おうおうにして頭でっかちな議論におちいりがちなのですが、そこには不安定なじぶんたちの立場に、ひとつの形をあたえたいという欲求のようなものがあったように思います。
そんななかで、自分の家族ではないハンディのあるひと(こども、老人、障害者)とかかわり、サポートしていくこととはどういうことなのだろう?といった素朴であるけれどむずかしい問題が、いつも頭のはしにありました。
そんなときに、先輩からすすめられたのが、本多勝一の著作でした。
「母親に殺される側の論理」というその文章は、じぶんの母親が脳性まひのある妹と心中をしようとした回想からはじまり、世間で起きた母親の子殺しについて、殺される側の脳性まひ者自身があげたことばを取りあげています。
それは、重い障害をもつ子どもを殺した母親の減刑を願う世論にたいし、そういった重度の障害者は殺されても仕方がないという価値感が問題なのだという提起です。
わたしたちは、社会福祉を学ぶうえで、「面倒をみたり、みられたり」という個人的な関係から、もっとレベルのちがう社会的な関係性をもってこなければ、現状を理解できないし、改善できないということを知ります。
それは、ある「構造」が、その構造ゆえに「貧しさ」や「苦しさ」がなくならず、さらに多くの「貧しさ」や「苦しさ」が生み出されていくといった仕組みのことです。
脳性まひ者の団体の名前が「青い芝の会」といいました。「青い芝の会」は1957年に設立され、はじめのうちはおもに親睦を目的とした団体だったようですが、1970年前後から社会的な発言や行動が活発になっていきます。その一端が、さきほどの親の障害児殺しへの発言でした。
「青い芝の会」の提起は、社会の不条理な「構造」を鋭くあらわしていました。多くの人が「あたりまえ」と考えていることのなかに、「死んでもしかたがない命」がふくまれているということです。
そして、それを不当として当事者が明らかにし、声を上げたということ。これはそれまでの「福祉」のあり方から一線を画していました。
戦後の障害児・者の福祉を牽引してきた人々も、不条理な「構造」を変えようとしてきました。そして、親たちと国を動かし「コロニー」を作り出しました。
しかし、障害のある本人の意向は聞かれず、それどころか重度障害者は意思がないものとしてすすめられたことが70年代になって大きく転換していきます。
その契機が「青い芝の会」の活動といえます。